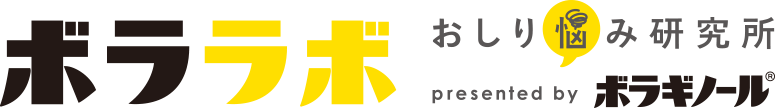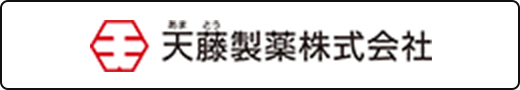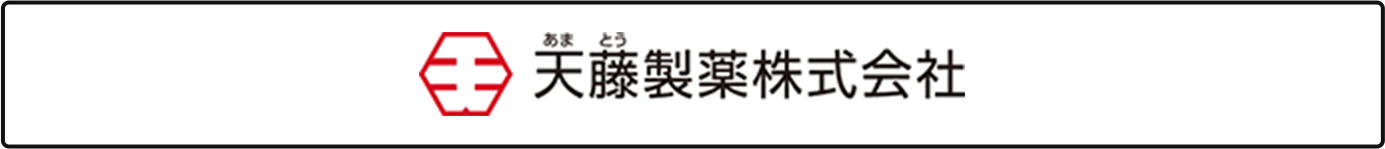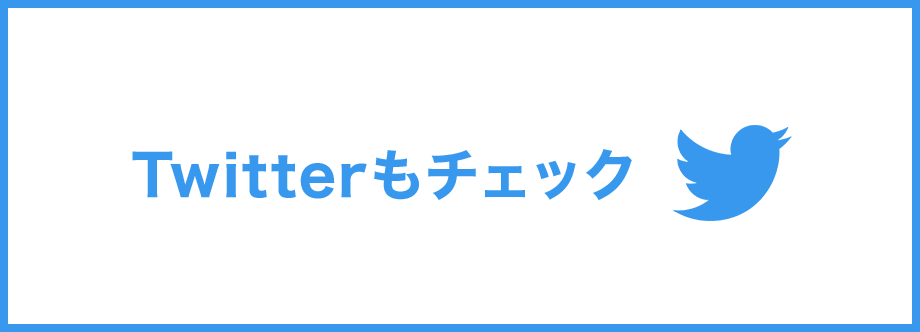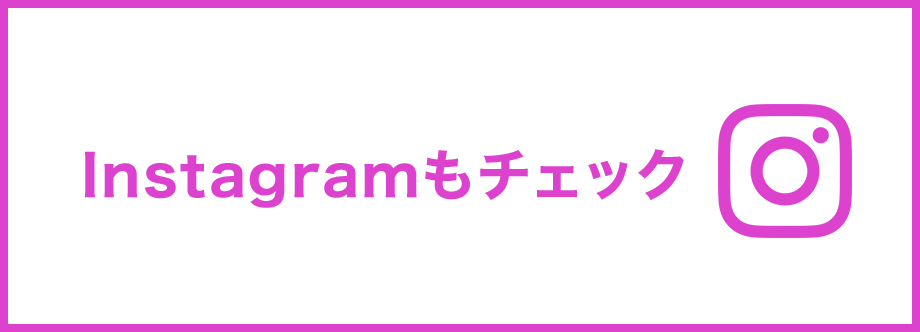痔に悩んだ偉人たち。
日本人編 戦国~江戸時代

加藤 清正
加藤清正は豊臣秀吉の子飼いの猛将(もうしょう)として知られ、熊本城の築城者として、また灌漑(かんがい)土木工事の大家として、“セイショコ(清正公)さん”の愛称をもって今日まで広く尊敬を集めています。
そして清正といえば虎退治で有名ですが、この猛将にも退治できなかった手強い相手がありました。
手強い相手といってもそれは人間や猛獣のことではなく、なんとおしりの病気“痔”のことです。
清正の痔はかなりひどく、一度トイレに入るとなかなか出られず、ときには1時間におよんだそうです。
土木の神様と呼ばれ、熊本での神様扱いはもちろん、江戸でも開運の神様と奉られた清正ですが、トイレに入っているときは“苦しいときの神だのみ”をしていたことでしょう。
どんなに強い人でも、どこかに必ず泣き所があるものなのですね。
参考文献:歴史探検隊「日本史はなしの玉手箱」文春文庫
大岡 忠相
大岡忠相(おおおかただすけ)は“名奉行 大岡越前守(えちぜんのかみ)”として、歴史書よりもむしろ演劇、講談、落語などで親しまれています。
しかし、公明で人情味あふれた忠相像は、実は後に創作された読み物「大岡政談(せいだん)」が創り出した虚像で、実際は常に冷静で、計算の行き届いた官僚の鑑(かがみ)のような人物であったそうです。
そんな忠相にもムキになってしまった事件がありました。
2日後に迫った公用の行事は痔の出血のため休みたい旨を行事責任者の稲生正武(いのうまさたけ)に告げると「今頃言ってもだめ」との返事。
カッとなった忠相は一方的に断わり、ついに行事は欠席。
その日の日記には「痔血走り、今日まかり出ず在宅」とあります。正武は忠相が日頃から面白く思ってない宿命のライバル。
結局行事は延期となったのですが、忠相の欠席の理由が本当に痔のためであったかはもう確かめることはできません。
でも、何だか親しみの持てる一件ですね。
参考文献:大石慎三郎「徳川吉宗とその時代」中公文庫
松尾 芭蕉
「持病さへおこりて、消入計(きえいるばかり)になん。」(「奥の細道」より)
(持病まで起こって、苦しみのあまり気を失いそうになった。)
東北、北陸、近畿地方にかけて約2,400kmを150日で歩き、名著「奥の細道」を残した松尾芭蕉の持病は、裂肛(きれ痔)と疝気(せんき=腹部の疼痛)でした。
上の文は、芭蕉が旅の途中、持病の激痛に襲われたときの心中を描いたものです。奥の細道の旅で芭蕉の痔は悪化し、出血も多くなり、発句どころではなかったようです。そのために西国への旅も延期されました。
そして、いよいよ西国…という矢先、芭蕉は食あたりが元でこの世を去っています。
参考文献:立川昭二「病いと人間の文化史」新潮選書
杉田 玄白
杉田玄白は70歳を過ぎても毎日歩いて往診に回り、83歳で「蘭学事始」を、84歳で「耄耋独語」(ぼうてつどくご:老いぼれの独りごと)を書き、翌年「医事は自然に如(し)かず」を残し、85歳で亡くなっています。
玄白は医学だけではなく、現代の理想の老後の先駆者でもありました。
その玄白にも悩みがあったのです。
「…いかなるか下の二穴(にけつ)のうるさくつらきことは、挙(あげ)て数へがたく…」 玄白は老人にありがちな秘結(ひけつ:便秘)で、便毎に脱肛をおこし、“元に納めて後、始めて我身の様に覚ゆる事なり”と、その苦痛を切々と「耄耋独語」に残しています。
玄白の脱肛は老人性のものか痔によるものかはっきりしていませんが、いずれにしても、その痛みは今も昔も同じことですよね。
参考文献:立川昭二「日本人の病歴」中央公論社